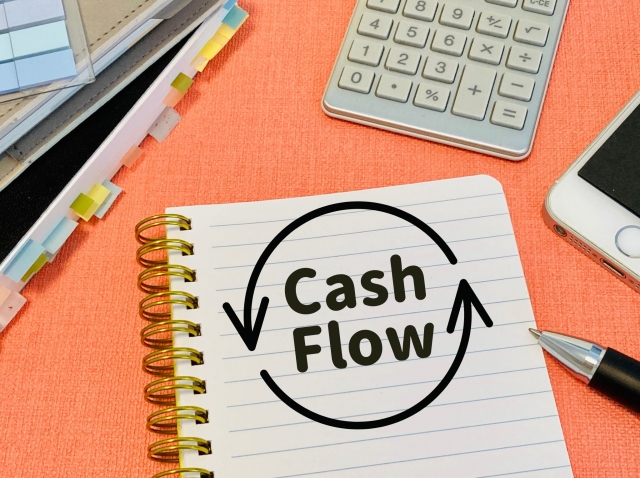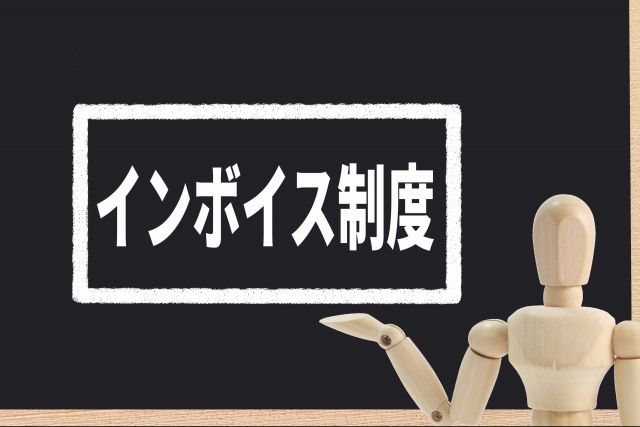経理担当初心者でも大丈夫!会計用語ゼロからスタートする収益・費用の基礎知識

目次
経理担当初心者でも大丈夫!会計用語ゼロからスタートする収益・費用の基礎知識
「会計」と聞くと、難しそうな専門用語や数字の羅列を思い浮かべる方も多いのではないでしょうか。
しかし、会社のお金の流れを理解するための基本は、とてもシンプルです。
この記事では、「収益」と「費用」という会計の出発点となる考え方を、
初めての方でもわかるようにやさしく解説します。
経理担当としてスタートしたばかりの方や、会計を勉強し始めた方がつまずきやすいポイントを整理しながら、
お金の流れを「見える化」する力を身につけましょう。
読み終えるころには、
数字が読める
経営の全体像がつかめる
そんな第一歩を踏み出せているはずです。
1.収益と費用の関係を理解する ― 「お金の流れ」の基本をつかもう
会社のお金の流れを理解するには、「収益」と「費用」の関係を知ることが大切です。
この2つは会計の基本です。どちらか一方だけを見ても、経営の実態はつかめません。
(1)利益の正体を知る
「利益=残ったお金」と思っていませんか。
実は、会計での利益はお金そのものではありません。
利益とは、利益とは、会社が一定期間でどれだけ成果を上げたかを示す数字であり、現金の増減を表すものではありません。
たとえば、12月に100万円の商品を販売し、入金が翌年1月なら、
お金はまだ入っていませんが、会計上は12月に収益が発生したとみなします。
同じように、費用も支払い日ではなく発生した時点で記録します。
このように、会計ではお金の動きより取引が起きたタイミングを重視します。
これを発生主義といいます。
利益=収益−費用
これが、会計を理解する第一歩です。
利益はお金の残りではなく、経営の結果を映す数字なのです。
(2)利益の段階を理解する
「利益」といっても、実はいくつかの種類があります。
それぞれの意味を理解すると、数字の背景が見えてきます。
売上総利益(粗利)
売上から仕入や原価を引いた利益です。
お店のがんばり度を示します。
営業利益
本業でどれだけ稼げたかを表します。
会社の本業の強さを知る数字です。
経常利益
本業に加え、利息や投資収益も含めた成果です。
会社全体の安定感を示します。
当期純利益
税金を差し引いたあとの最終的な利益です。
いわば結果を表す数字です。
どの利益を見るかは、目的によって異なります。
営業活動の改善を考えるなら「営業利益」。
会社全体の状態を知りたいなら「経常利益」。
最終的な成果を確認したいなら「当期純利益」。
このように使い分けることで、数字が「経営の判断材料」に変わります。
(3)利益でわかる会社の状態
利益を分析すると、会社の特徴や課題が見えてきます。
売上が増えても利益が減っている場合
費用が増えすぎている可能性があります。
売上が横ばいでも利益が安定している場合
固定費を上手に抑え、効率的に経営している会社です。
一時的に利益が急増した場合
資産の売却など、一度きりの要因かもしれません。
利益の数字は、会社の経営の癖を映します。
数字を眺めるだけではなく、なぜ増えたのか、どの費用が影響したのかを考えることが大切です。
(4)利益を身近に感じる考え方
会計の考え方は、実は私たちの日常と同じです。
たとえば、あなたの1か月を想像してみてください。
給料が30万円入り、生活費に25万円を使ったとします。
残りの5万円が、あなたの利益です。
会社も同じ仕組みです。
収益:入ってくるお金(売上など)
費用:出ていくお金(仕入・給料・家賃など)
利益:その差額。つまり残る力
会計は難しい特別なものではありません。
お金の流れを整理して見える化する仕組みです。
この考え方がわかると、数字が身近に感じられるようになります。
利益は、会社の活動を映す鏡です。
「収益」と「費用」の関係を理解することが、会計の第一歩となります。
2.会計の視点で見る「収益」と「費用」 ― 現金の動きとは違う世界
会社のお金の流れを見誤らないためには、現金の増減だけを見てはいけません。
会計の世界では、「お金の動き」と「収益・費用の発生」を区別して考えます。
それがわかると、数字のズレや誤解に気づけるようになります。
(1)会計は「発生主義」で成り立っている
会計では、現金の出入りのタイミングとは別に取引を記録します。
これを発生主義といいます。
たとえば、商品を販売したけれど、代金をまだ受け取っていない場合でも、
その時点で「売上(収益)」として計上します。
逆に、仕入れをして代金をまだ払っていない場合でも、
その時点で「仕入(費用)」として計上します。
このように、実際にお金が動く時期と、取引を会計処理する時期はずれているのです。
この考え方を理解することが、会計の基本です。
(2)「現金主義」との違いを具体例で考える
発生主義を理解するには、2つの考え方を比較してみましょう。
現金主義:
現金の出入りの事実に注目します。
・お金を受け取ったら「収益」、支払ったら「費用」として扱う。
・シンプルですが、実態を正確に把握できないことがあります。
発生主義:
取引の発生のタイミングで記録します。
・お金を受け取っていなくても「収益」を計上。
・お金を払っていなくても「費用」を計上。
・ズレがある分、期間ごとの業績を正確に評価しやすくなります。
たとえば、12月に売上があって1月に入金があった場合、
現金主義では1月の収益ですが、発生主義では12月の収益になります。
これが、経理上で月次の数字がズレて見える理由のひとつです。
(3)「売掛金」と「買掛金」を意識しておく
多くの取引では、現金の受け渡しが後になります。
これが売掛金と買掛金の考え方です。
売掛金:商品やサービスを販売したが、まだ代金を受け取っていないお金
買掛金:商品を仕入れたが、まだ代金を支払っていないお金
たとえば、12月に販売して翌年1月に入金される場合、
売上は12月の「収益」、売掛金は「資産」として記録されます。
このように、会計ではお金が入ってくる前の権利・出ていく前の義務も数字に反映されるのです。
(4)「費用」と「支出」を区別して考える
混同されがちですが、「費用」と「支出」は別のものです。
費用:その期間の成果を得るために使ったコスト
支出:実際にお金を支払った行為
たとえば、材料を購入して倉庫に保管している場合、
支出は発生していますが、まだ販売していないため「費用」にはなりません。
在庫として「資産」に計上されます。
一方、仕入れた材料を使って商品を販売した時点で、
初めて「費用」として記録されます。
このように、会計では支出のタイミングよりも、
成果に結びついた時点で費用を認識するのです。
(5)会計の視点を持つと数字が鮮明に見える
現金の出入りだけを見ていると、経営の本当の姿が見えません。
発生主義の視点を持つことで、売上・費用・利益の関係が明確になります。
・「売上はあったのにお金が足りない」理由がわかる
・「支出が多いのに赤字ではない」仕組みが理解できる
・「利益が出ているのに現金が減る」原因を説明できる
会計の目的は、単に数字を並べることではありません。
企業活動の結果を正確に表すためのルールです。
お金の流れと会計の考え方の違いを理解すれば、
経営判断や日常の数字の見方が格段に変わります。
3.数字を読む力を身につける―損益計算書の理解と活用
会社の数字を読めるようになると、経営の状態が一目でわかります。
その第一歩が損益計算書(P/L)です。
難しそうに聞こえますが、仕組みを理解すれば数字の流れは驚くほどシンプルです。
(1)損益計算書は会社の成績表
損益計算書は、会社の1年間(または1か月)の経営活動をまとめた報告書です。
どれだけ収益を上げ、どれだけ費用を使い、どれだけ利益が残ったかが一覧でわかります。
これは、学校の通知表に近いものです。
科目名の代わりに「売上」「経費」「利益」といった項目が並びます。
数字を見るだけで、会社の頑張りや課題が浮かび上がります。
(2)損益計算書の読み方を身につける
最初に見るべきポイントは、数字の流れです。
上から下に向かって、収益→費用→利益と並びます。
これは会社のお金の動きをそのまま表しています。
数字を追うときは、次の3点を意識しましょう。
- 売上高:会社がどれだけ稼いだか
- 営業利益:本業でどれだけ成果を出せたか
- 当期純利益:最終的にどれだけ残ったか
この3つを確認するだけでも、会社の健康状態が見えてきます。
(3)増えた・減っただけで判断しない
数字を見るときに大切なのは、単なる増減に注目しないことです。
数字が大きくなっても、それが良い結果とは限りません。
売上が伸びても広告費や人件費が増えれば、利益は減ります。
反対に、売上が少し落ちてもコスト削減で利益が増えることもあります。
重要なのは「なぜそうなったのか」を考えること。
数字の裏には必ず原因があります。
損益計算書を読むとは、その背景を読み解くことなのです。
(4)構成比と推移を見るクセをつける
損益計算書を理解するもう一歩先のコツは、割合と変化を見ることです。
構成比を見る:
売上に対して、どの費用がどのくらいの割合を占めているかを確認します。
たとえば、人件費が売上の50%を超えていれば、固定費が重い構造といえます。
推移を見る:
前年や前月と比べ、数字がどう変化しているかを見ます。
一時的な増減ではなく、数か月・数年単位の動きを追うことが大切です。
こうした比較を続けると、会社の体質や傾向が自然と見えてきます。
(5)初心者でもできる実践的な見方
損益計算書は経理担当だけでなく、経営者やスタッフにも役立ちます。
専門知識がなくても、次の3つを意識するだけで理解が深まります。
- 毎月の損益計算書で売上・費用・利益の3項目をチェックする
- 前期と比べてどの数字が大きく動いたかを確認する
- 気づいた点を記録し、翌月も比較する
これを繰り返すことで、自然と数字を読む感覚が育ちます。
数字は慣れるほど、理由を語り始めます。
(6)数字を見る習慣が経営を変える
会計の知識は、経営判断の精度を高めます。
数字を読めるようになると、感覚ではなく根拠をもとに行動できるようになります。
次のような判断が、数字から導けるようになります。
- 新しい投資をしても良いか
- コスト削減の余地はあるか
- 今の経営は利益を生んでいるか
損益計算書は、これらの判断を支える「経営の地図」です。
数字を読む力を育てることは、会社の未来を守る力を育てることでもあります。
損益計算書は、単なる報告書ではありません。
そこには会社の努力、戦略、そして日々の積み重ねが数字として刻まれています。
数字を読めるようになること――それが、経営を理解する最も確かな一歩です。
まとめ
会計はむずかしく見えても、基礎はシンプルです。
大切なのは、収益と費用の関係を正しくつかみ、利益の中身を理解すること。
ここがわかると、数字は一気に読みやすくなります。
ポイントは3つだけ
- 利益の正体:お金の残りではありません。一定期間の成果を表す数字です。
- 発生主義の視点:現金の出入りと記録のタイミングはずれることがある。このズレを理解すると、黒字なのに現金が足りない理由が見えます。
- 損益計算書の要所:まずは売上高→営業利益→当期純利益の流れを追う。構成比と推移を見るクセをつけると、体質と変化がつかめます。
よくあるつまずきはココ
- 入金=収益と思いがち
収益は成果が生まれた時点で計上します。 - 支出=費用と思いがち
費用は価値を使った時点で計上します(例:減価償却や在庫)。 - 増減だけで判断しがち
数字が動いた理由を必ず見る。広告費・人件費・原価などの内訳を確認。
明日からできる3ステップ
- (1)月次P/Lを1枚見る
売上高・営業利益・当期純利益の3点にマーカーを引く。 - (2)前月・前年と比べる
大きく動いた科目を1つだけ特定し、理由をメモする。 - (3)行動に落とす
コストなら固定費か変動費かを切り分け、小さな施策を1つ決める。
結局、会計は“見える化の技術”。
収益・費用・利益のつながりを押さえ、発生主義でズレを理解し、P/Lで変化を追う。
この流れができれば、数字は意思決定の味方になります。
焦らず、まずは3つの言葉(収益・費用・利益)を自分の言葉で説明できるようにする。
そこから、一歩ずつ前へ進みましょう。