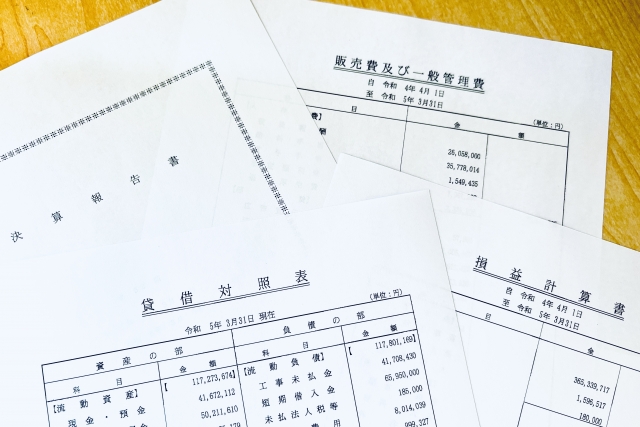経理担当者は経営の参謀!?~数字から会社を強くする方法~

経理担当者は経営の参謀!?~数字から会社を強くする方法~
「経理は過去を記録するだけの仕事だ。」
もしあなたがそう思っているなら、その考えを今すぐ捨ててください。経理が扱う数字は、単なる帳簿の記録ではありません。それは会社の過去を映し出す鏡であり、未来を照らす羅針盤です。本記事では、経理の仕事がいかに会社を強くする戦略的な役割を担っているかを解説します。財務三表だけではない多角的な視点から会社の真の姿を読み解き、数字の羅列ではなく「ストーリー」として経営陣に提言する、そんな「攻めの経理」への道をご紹介します。
1.経理は「過去の記録」じゃない!
多くの企業では経理部門は「バックオフィス」として、日々の取引記録や請求書の処理といったルーティンワークに追われています。もちろん、これらの業務は会社の健全な運営に不可欠です。しかしそれだけで終わってしまっては、経理が持つポテンシャルを最大限に活かせているとは言えません。経理の真の価値は単に帳簿をつけることや、税金の計算をすることではありません。経理が扱う数字は会社の未来の方向性を決める、最も重要な経営資源なのです。
(1)過去の数字が語りかける未来のヒント
あなたの会社の会計データは、単なる数字の羅列ではありません。それは、事業活動のあらゆる側面にわたる詳細な「物語」を語っています。
【売上データ】
どの商品が、どの顧客層に、いつ、どれだけ売れているのか?
【コストデータ】
どの部門で、どのような費用が発生しているのか? 費用対効果の高い投資はどれか?
【キャッシュフロー】
資金繰りは安定しているか? 将来の投資に必要な資金は確保できているか?
これらのデータは、過去の事実を示しているだけではありません。未来を予測し、戦略を立てるための貴重なヒントが隠されています。例えば過去の売上データを分析することで、特定の季節やイベント時に売上が伸びる傾向を発見できるかもしれません。その傾向を活かして次の販促キャンペーンを計画すれば、より高い効果が期待できます。また、コストデータを詳細に分析することで無駄な経費を見つけ出し、コスト削減の余地を発見できます。さらにどの部門の生産性が高いかを把握すれば、その成功事例を他の部門へ展開することも可能です。
(2)「守りの経理」から「攻めの経理」へ
従来の経理業務は法的な要件を満たし、正確な財務報告を行う「守りの経理」が中心でした。しかし現代のビジネス環境においては、これだけでは不十分です。これからの経理担当者に求められるのは数字を分析し、そこから得られた洞察を経営陣に提言する「攻めの経理」へのシフトです。具体的なアクションとしては、以下のようなことが挙げられます。
【リアルタイムな業績把握】
月次決算を迅速化し、最新の業績をタイムリーに把握できる仕組みを構築する。
【多角的な分析レポートの作成】
損益計算書(P/L)や貸借対照表(B/S)だけでなく、顧客別、商品別、部門別の売上や利益率など、経営判断に役立つ多角的なレポートを作成する。
【予測とシミュレーション】
過去のデータに基づき、将来の売上や利益を予測するシミュレーションを行い、様々なシナリオを想定した経営計画をサポートする。
【他部門との連携強化】
営業、マーケティング、製造といった他部門と積極的にコミュニケーションを取り、数字の背景にある「現場」の状況を理解する。
(3)羅針盤としての経理が会社を強くする
経営の羅針盤としての役割を担う経理は、単なる記録係ではありません。過去の数字を深く理解し、未来の方向性を示す戦略パートナーです。経理担当者が数字から会社の強みや弱み、潜在的な機会やリスクを読み解きそれを経営陣に分かりやすく伝えることができれば、より精度の高い、素早い意思決定が可能になります。それは会社全体の競争力を高め、持続的な成長を実現する上で不可欠な要素です。経理の仕事は過去を振り返るだけでなく、未来を創る仕事です。さあ、あなたも「攻めの経理」として数字の力で会社を強くしていきませんか?
2.会社を強くする3つの視点
経理担当者にとって、財務三表(P/L、B/S、C/F:キャッシュフロー計算書)は会社の健康状態を知る上で欠かせないものです。しかしそれらの数字だけを追っていても、会社の「なぜ?」や「どうすれば?」は見えてきません。例えば、損益計算書(P/L)で売上が伸びていることが分かっても、「なぜ伸びたのか?」「誰が買ってくれたのか?」までは分かりません。貸借対照表(B/S)で資産が増えていても、「その資産は将来の利益につながるのか?」という問いには答えられません。この記事では財務三表の数字に加えて、会社をより深く多角的に分析するための3つの視点を紹介します。これらの視点を取り入れることで、経理は単なる記録係から経営の未来を創る参謀へと進化できます。
(1)「顧客」から見る視点 → 売上を支えるストーリーを読み解く
財務三表は会社全体の業績をマクロな視点から捉えますが、個々の顧客の行動は捉えられません。そこで重要になるのが、顧客データを分析する視点です。
【顧客一人あたりの単価(客単価)】
売上を顧客数で割った数字です。客単価が低い場合、より高価な商品を提案したりセット販売を導入したりする戦略が考えられます。
【リピート率】
一度購入した顧客が、再び購入してくれる割合です。リピート率が高いほど、顧客ロイヤルティが高い健全なビジネスモデルと言えます。逆に低い場合は、顧客満足度や商品・サービスの質を見直す必要があります。
【顧客獲得コスト(CAC)】
新規顧客を一人獲得するためにかかった費用です。CACが高い場合、広告戦略の見直しや、より効率的な集客方法を検討するきっかけになります。
これらの数字を分析することで「どの層の顧客が優良なのか?」「どうすればリピーターが増えるのか?」といった、売上を支える具体的なストーリーが見えてきます。
(2)「生産性」から見る視点 → 効率的な経営への道筋をつける
コスト削減は重要ですが、ただ経費を削るだけでは会社の成長は止まってしまいます。真に会社を強くするには、生産性を高める視点が不可欠です。
【従業員一人あたりの粗利益】
従業員がどれだけの利益を生み出しているかを示す指標です。この数字が低い場合、業務の無駄がないか、適切な人員配置ができているかを見直す必要があります。
【営業担当者一人あたりの売上】
営業部門の生産性を測る上で重要な指標です。この数字が低い場合、営業ツールの見直しや教育体制の強化が求められます。
【棚卸資産回転率】
在庫がどれだけ効率的に販売されているかを示す指標です。この回転率が低い場合、過剰な在庫を抱えていないか確認し、在庫管理の改善や仕入れ量の最適化を検討します。
生産性を測るこれらの指標は財務三表だけでは見えてこない、業務プロセスのボトルネックや改善点を浮き彫りにします。
(3)「部門別」から見る視点 → 会社全体の最適化を図る
会社全体の数字であるP/LやB/Sだけではどの部門が利益を生み出し、どの部門に課題があるのかを正確に把握するのは困難です。部門別の視点を持つことで、会社の全体像をより鮮明に描き出せます。
【部門別の売上・利益】
どの部門が会社の収益を牽引しているのか、逆にどの部門が赤字を生んでいるのかを可視化します。
【部門別の経費】
どの部門でどのような経費が使われているかを細かく把握することで、無駄な支出を発見し、予算配分の最適化につなげられます。
【部門間の連携指標】
部門間のコミュニケーション頻度やプロジェクトの進捗度合いなど、数値化しにくい定性的な指標も重要です。これにより、組織全体の連携を高めるための課題が見えてきます。
部門別の数字は各部門の成果を正しく評価し、最適なリソース配分を行うための根拠となります。
(4)財務三表は「入口」、詳細分析が「本質」
P/L・B/S・C/Fは、あくまで会社の財務状況を大まかに把握するための「入口」です。その数字の裏側にある「顧客の行動」「業務の生産性」「部門ごとの貢献度」といったより詳細な分析こそが、会社の課題を特定し未来の成長戦略を策定するための「本質」となります。経理担当者がこれらの多角的な視点を持つことで、単なる過去の記録係から経営の未来を切り拓く真のパートナーとなることができるのです。
3.経営陣への提言は「ストーリー」で語る
経理担当者が経営の参謀として活躍するためには、どれだけ緻密に数字を分析しても、内容が経営陣に伝わらなければ意味がありません。
「売上が前年比5%増加しました。」「人件費が予算を10%超過しました。」
このような数字の羅列だけでは、経営陣は「ふーん、それで?」となってしまいがちです。なぜなら数字そのものは「事実」を伝えるだけで、その背景にある「なぜ」やこれからどうすべきかという「行動」を示していないからです。数字の力を最大限に活かすには数字の羅列ではなく、課題と解決策を明確にした「ストーリー」で語ることが不可欠です。経理は数字という「データ」と、その背景にある「物語」を結びつける語り部なのです。
(1)結論から語る「ピラミッド構造」
経営陣は多忙です。詳細な説明から始めると、途中で聞く気をなくしてしまうかもしれません。プレゼンの基本は、まず結論から伝える「ピラミッド構造」です。
【NG例】
「まず、2024年4月の広告費が前年同月比で30%増加しました。内訳を見ると、SNS広告の費用が特に伸びています。次に、SNS広告からの新規顧客獲得数を分析すると、前年より10%減少しています。そのため、広告の費用対効果が大幅に悪化していることが分かります…。」
【OK例】
「**結論から申し上げます。当社のSNS広告は費用対効果が急激に悪化しており、直ちに広告戦略の見直しが必要です。**その根拠として、4月の広告費が30%増加したにもかかわらず、新規顧客獲得数は10%減少しています。このままでは、今後も無駄なコストが増え続けます。」
このように、最初に結論を提示することで経営陣は「今から何の話を聞くのか」を瞬時に理解できます。その後に根拠となる数字を提示することで、説得力が格段に増します。
(2)数字に「意味づけ」をする
ただ数字を並べるだけでなく、その数字が持つ意味を解説することが重要です。
☆「事実」と「解釈」をセットで伝える
・事実 → 「新規顧客獲得コスト(CAC)は1万円に上昇しました。」
・解釈 → 「これは昨年と比較して2倍のコスト増であり、現状の広告戦略では利益を圧迫する水準に達しています。」
☆他社や目標との比較で「基準」を示す
・事実 → 「売上高利益率は5%でした。」
・意味づけ → 「これは業界平均の10%を大きく下回っており、当社の収益構造に課題があることを示しています。」
このように単なる数字に「比較」や「解釈」を加えて意味を持たせることで経営陣はより深く、そして迅速に状況を理解できます。
(3)解決策を具体的に「提案」する
ストーリーのクライマックスは、課題の解決策です。単に「どうにかすべきです」と言うのではなく、具体的な提案まで踏み込むことで経理は「提言者」としての価値を発揮します。
【NG例】
「このままではいけないので、何か対策を講じる必要があります。」
【OK例】
「この状況を打開するため、SNS広告の予算を20%削減し、費用対効果の高いリスティング広告への予算シフトを提案します。これにより、今後3ヶ月で新規顧客獲得コストを5,000円まで改善できると試算しています。」
このように、「課題 → 原因 → 解決策 → 期待される効果」という一連の流れでストーリーを組み立てることが重要です。提案にはコストや期待効果といった数字を必ず盛り込み、経営判断をしやすいように補足しましょう。
(4)経営陣が抱える「問い」に答える
経理の分析レポートは経営陣が知りたいこと、つまり「問い」に答える形で作成すべきです。
「売上を伸ばすにはどうすればいいか?」「コスト削減の余地はどこにあるか?」「新たな投資は本当に必要なのか?」
これらの問いを常に意識し、経営陣の意思決定を後押しするようなデータとストーリーを準備しておくことが、経理の価値を最大化します。数字の羅列は情報に過ぎませんが、ストーリーは「行動」を促します。経理が語るストーリーは経営陣の心を動かし、会社を前進させる原動力となるのです。
4.まとめ
経理の仕事は、決して過去の記録係ではありません。日々の数字を正確に記録する「守りの経理」の役割はもちろん重要ですが、それだけでは経理の真価は発揮されません。経理が扱う数字には、未来への貴重なヒントが隠されています。
財務三表の数字を単なる情報として眺めるのではなく「顧客」「生産性」「部門」といった多角的な視点から深く分析することで、会社の強みや弱みが浮き彫りになります。そしてその分析結果を単なる数字の羅列ではなく、課題と解決策を明確にした「ストーリー」として経営陣に提言すること。これが、未来を創る「攻めの経理」への道です。
経理とは過去のデータを分析し、未来の経営戦略を策定するための基盤を築くという役割があります。数字の背景にある物語を読み解き、それを伝える語り部になることで経営の意思決定を支え、会社の成長を加速させる戦略パートナーへと進化できます。さあ、あなたも「攻めの経理」として数字の力で会社を強くしていきませんか?