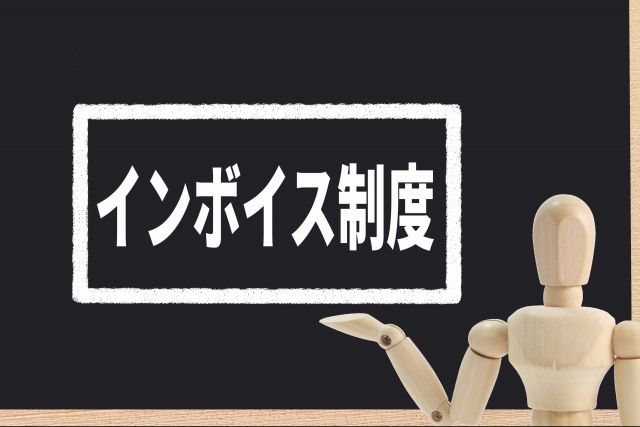インボイス制度におけるインボイスの記載事項とは?従来との違いや注意点も解説

目次
はじめに
2023年10月1日から、消費税のいわゆるインボイス制度が始まりました。それに伴い、「インボイス(適格請求書)」を受領し保存しない限り、課税事業者は、仕入税額控除を受けることができなくなりました。
受け取った領収書についても、簡易的な適格請求書として利用が認められ、適正な領収書をもとに仕入税額控除が可能となります。
ただし、適格請求書(インボイス)として認められるためには満たすべき要件が法定されているため、事前に整理しておく必要があります。
そもそもインボイス制度とは
-
仕入税額控除
消費税は消費者が負担しますが、納税は課税事業者が行います。課税事業者は、売上げに係る消費税額から、仕入れに係る消費税額を差し引いて計算した額を納税します。
売上で受け取った消費税額から、仕入れで支払った消費税額を差し引くことを「仕入税額控除」と言います。
具体的には、消費税として税務署に納める金額は、次の計算方法で計算します(原則課税)。
-
インボイス制度の概略
2023年10月にインボイス制度がはじまると、この仕入税額控除をするためには、原則として、仕入先からインボイス(適格請求書)を発行してもらい、保存しておく必要があります。
このインボイスは、税務署長の登録を受けたインボイス発行事業者(登録事業者)のみが発行できます。つまり、仕入先にインボイスを発行してもらうには、仕入先が税務署にインボイス事業者として登録する必要があります。つまり、仕入先がインボイス発行事業者であるか確認する作業が必要となってきます。
仮に、仕入先がインボイス発行事業者ではなかった場合、そこから仕入れた取引は、仕入税額控除ができず納税する消費税の額が増えてしまいます。
売り手と買い手の義務
<売手側>
売手である登録事業者は、買手である取引相手(課税事業者)から求められたときは、インボイスを交付しなければなりません(また、自らが交付したインボイスの写しを保存しておく必要があります)。
<買手側>
買手は仕入税額控除の適用を受けるために、原則として、取引相手(売手)である登録事業者から交付を受けたインボイスの保存等が必要となります。
ただし例外として、買手はインボイスの保存に代えて、買手が自ら作成した仕入明細書等のうち「一定の事項(インボイスに記載が必要な事項)が記載され取引相手の確認を受けたもの」を保存することで、仕入税額控除の適用を受けることもできます。
経過措置
インボイス制度の開始後6年間(2029年9月まで)は、免税事業者等が発行する従来の区分記載請求書等に基づき、一定の割合で仕入税額控除ができる措置が設けられています。
経過措置については、別記事「インボイス制度の経過措置とは?」に詳しく説明しております。
インボイス登録の方法
税務署に対して、「適格請求書発行事業者の登録申請書」を提出し、インボイス登録番号を発行してもらう必要があります。
申請は、紙での提出、またはe-Taxで行うことができます。
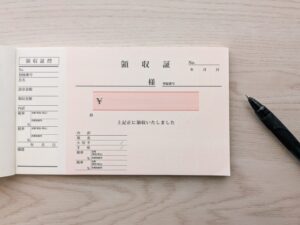
適格請求書(インボイス)の記載事項
適格請求書(インボイス)の様式は法令又は通達等で定められておらず、必要な事項が記載された書類であれば請求書、領収書、納品書といった名称を問いません。また、手書きであってもインボイスに該当します。
適格請求書として認められるには、以下6つの事項の記載が必要です。
1、適格請求書発行事業者の氏名または名称および登録番号
2、取引年月日
3、取引内容(軽減税率の対象品目である旨)
4、税率ごとに区分して合計した対価の額(税抜き又は税込み)および適用税率
5、税率ごとに区分した消費税額等
6、書類の交付を受ける事業者の氏名または名称
ここで注意が必要なのは、「5、税率ごとに区分した消費税額等」です。
インボイス制度では、取引に係る税抜価額又は税込価額を税率ごとに区分して合計した金額に対して、10%又は8%(税込みの場合は10/110又は8/108)を乗じて得た金額に対して端数処理を行い「消費税額等」を算出します。
したがって、適格請求書の記載事項である「税率ごとに区分した消費税額等」に1円未満の端数が生じる場合には、一の適格請求書につき、税率ごとに1回の端数処理を行います。この 端数処理は、「切上げ」、「切捨て」、「四捨五入」など任意の方法で行うこととなります。
従来のように、品目ごとに端数処理をすることができなくなりましたので、注意が必要です。
※下記のリンクのPDFの5ページ目に画像付きの解説があります。
-https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/0020006-027.pdf
従来の区分記載請求書の記載事項
2023 年 9 月末で終了した区分記載請求書の記載事項では、従来の記載事項となる①~⑤の項目に加え、 ⑥、⑦の記載事項 が必要となりました。
①発行者の氏名または名称
②取引年月日
③取引内容
④取引金額
⑤交付を受けるものの氏名または名称
⑥軽減税率の対象品目である旨
⑦適用税率 (8%・10%) 及び税率ごとに区分して合計した取引の額 (税込)
インボイスと従来の区分記載請求書との違い
記載事項の違い
適格請求書については、従来の区分記載請求書に、以下 2 点の項目を追加したものとなっています。また、適格請求書では、税率ごとに区分して合計した取引の額は税抜もしくは税込で記載ができます。
適格請求書発行事業者の氏名または名称および登録番号
税率ごとに区分した消費税額等
適格請求書発行事業者への登録が必要
適格請求書では、請求書に「登録番号」を記載する必要があります。
すなわち、適格請求書(インボイス)を発行する側は、管轄の税務署長に登録申請書を提出しなければなりません。事業者登録が完了すると、登録番号が発行され適格請求書に記載することができます。
インボイス制度のもとでは得意先(買い手側)が仕入控除制度の適用を受けるためには、適格請求書(インボイス)が必要となります。そのためには、インボイス事業者の登録が必須です。

電子インボイス
国税庁のパンフレットによれば、適格請求書は、書面での交付に代えて、電磁的記録(電子データ)で提供することができます(電子インボイス)。
適格請求書に係る電磁的記録の記録事項は、書面で適格請求書を交付する場合と同じです。
そして、インボイスに係る電磁的記録の提供方法の具体例として、EDI取引(受発注に係るオンラインシステムを介した連絡)、電子メール送信、インターネット上のサイトを通じた提供、記録用媒体での提供などが挙げられています。
インボイス制度における「領収書」の注意点
そもそもインボイス=適格請求書とは、買い手に正しい適用税率・消費税額などを伝えるための手段を指します。したがって、要件を満たすなら書類の名称は問われません。請求書でなく、納品書や領収書などでもよいのです。
また、適格請求書は、一の書類のみで全ての記載事項を満たす必要はありません。例えば、請求書と納品書など、相互の関連が明確な複数の書類全体で記載事項を満たしていれば、これら複数の書類を合わせて一の適格請求書とすることが可能です。
交付を受けた買い手は、要件を満たす領収書等をインボイスとして保存しておくことで仕入税額控除の適用を受けられます。(交付した売り手側も写しの保存が必要です。)
なお、個人事業主や中小企業においては、BtoB取引を除くと、一般の領収書やレシートは、ほとんどが「簡易」インボイスになると思われます。簡易インボイスは、不特定多数の人たちに販売・サービス提供を行う事業者のみ発行が認められています。
取引価格が3万円未満でもインボイスが必要
これまでは仕入税額控除の特例として、取引価格が3万円未満の場合、領収書などがなくても法定事項が記載された帳簿の保存のみで仕入税額控除が認められていました。
しかし、インボイス制度が導入された後は、3万円未満の取引でもインボイスが必要になります。
インボイスが不要な場合
ただし、このうち3万円未満の特例的な扱いが残るものが下記の二つです。
1.公共交通機関による旅客の運送(公共交通機関特例)
2.自動販売機及び自動サービス機からの商品の購入(自動販売機特例)
※この特例を受けるための帳簿記載事項は、下記の通りです。
1.課税仕入れの相手方の氏名又は名称
2.課税仕入れを行った年月日
3.課税仕入れに係る資産又は役務の内容
4.課税仕入れに係る支払対価の額
5.「3万円未満の鉄道料金」、「〇〇市 自販機」、「××銀行□□支店ATM」などの記載
【具体例】
2025年3月15日 〇〇鉄道株式会社 運賃 3万円未満の公共交通機関 500円
なお、インボイス制度下でインボイスが不要な場合については、下記記事の「5,帳簿のみの保存が認められる場合」に詳しく説明しております。
「インボイス制度で領収書の3万円未満の特例はどうなる?変更点について解説」
まとめ
2023年10月からのインボイス制度の導入により、仕入税額控除を受ける方法が変わります。売り手は書面または電子データによる適格請求書(インボイス)の交付に対応し、これを発行する義務があります。
買い手側は、仕入税額控除の適用を受けるために適格請求書を保存することが必須となります。インボイスに記載された適格請求書発行事業者の登録番号を検索照合し、仕入税額控除が可能かどうかの確認をする作業が必要となり、事務作業の増加が予想されます。
執筆者:税理士 渕上 肇