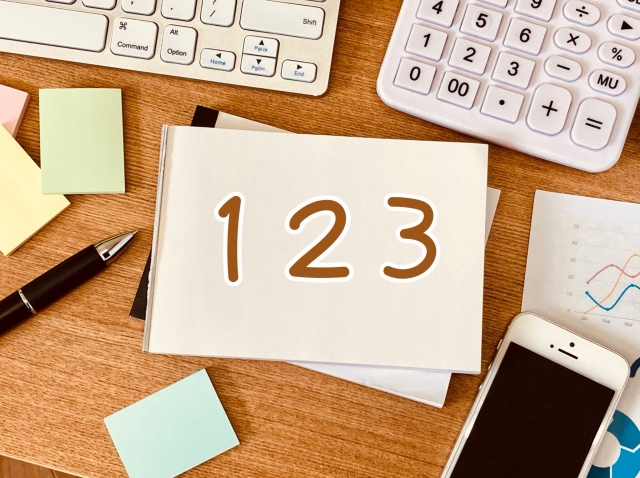融資を受ける前に知っておきたい決算書の見られ方

融資を受ける前に知っておきたい決算書の見られ方
経営者の皆さん、事業拡大や新たな挑戦のため資金調達を検討していませんか?金融機関に「融資」を申し込む際、必ず提出を求められるのが「決算書」です。これは会社の成績表であり、金融機関はここから会社の健康状態を読み解き、融資の可否を判断します。しかし「うちの決算書、どう見られているんだろう…?」と不安に思う方も少なくないでしょう。本記事では、金融機関が特に重視するチェックポイントをわかりやすく解説します。決算書を単なる報告書ではなく、会社の未来を語るための大切なツールに変えるヒントをお届けしますので、ぜひ最後までお読みください!
1.決算書の「健康診断」チェックポイント
融資を申し込む際、決算書は会社の健康状態を映し出す「カルテ」のようなものです。銀行員は、このカルテから会社の「財務の健全性」を細かくチェックし、融資の可否を判断します。病気のカルテが体の状態を正確に語るように、決算書は会社の「収益性」「安全性」「資金繰り」を正確に示します。この記事では、決算書から見るべきポイントを解説していきます。
(1)損益計算書(P/L)から見る「収益性」の評価
損益計算書(P/L)は、会社の収益力を示します。ここで最も重視されるのは、やはり売上高と経常利益です。売上高が毎年安定して伸びているか、あるいは急激に減少していないかを確認します。また経常利益は本業での儲けを示すため、これが安定して黒字であることは会社の収益性が高いと判断される重要な要素です。
【売上総利益率(粗利率)】
売上高から売上原価を引いた利益の割合です。これが高いほど、商品やサービスの競争力が高いと評価されます。
【経常利益率】
売上高に占める経常利益の割合です。この数字が高いと、本業でしっかりと利益を上げられている健全な会社と見なされます。
(2)貸借対照表(B/S)から見る「安全性」の評価
貸借対照表(B/S)は会社の財産状況を示します。ここでは会社の「安全性」、つまり倒産しにくい体質であるかが評価されます。
【自己資本比率】
総資産に占める自己資本の割合です。この数字が高いほど、借金に依存せず会社の力で経営していると判断されます。一般的に20%以上が健全な目安とされています。
【流動比率】
会社の短期的な支払い能力を示す指標です。「流動資産 ÷ 流動負債」で計算され、150%以上あると資金繰りに余裕があると判断されます。
【固定長期適合率】
長期的な資金繰りの安定性を示す指標です。「固定資産 ÷(自己資本 + 固定負債)」で計算され、100%を下回ると安定した資金で固定資産を賄っていると評価されます。
(3)キャッシュフロー計算書(C/F)から見る「資金繰り」の評価
キャッシュフロー計算書(C/F)は、お金の流れ(キャッシュ)に注目した書類です。利益が出ているのに手元にお金がない「黒字倒産」を防ぐ上で、キャッシュフローは非常に重要です。
【営業活動によるキャッシュフロー】
本業でどれだけお金を稼いだかを示します。これがプラスであれば、事業活動が順調にお金を創出している証拠です。
【投資活動によるキャッシュフロー】
設備投資や資産売却など、投資活動によるお金の動きを示します。
【財務活動によるキャッシュフロー】
借入や返済、増資など、資金調達によるお金の動きを示します。
特に銀行員は、営業活動によるキャッシュフローが継続的にプラスであるかを注視します。これが安定していれば、借入金の返済能力が高いと判断されます。
(4)決算書は「未来」を語るためのツール
銀行員はこれらの数字を単体で見るのではなく、複数の指標を組み合わせて多角的に分析します。例えば、自己資本比率が低くても営業活動によるキャッシュフローが安定していれば、返済能力が高いと判断されることもあります。また、決算書は過去の経営結果にすぎません。これらの数字を基に「今後、会社をどう成長させていくか」を具体的に説明することが、融資成功への鍵となります。決算書をただの書類として提出するのではなく、自社の強みや弱みを正確に把握し未来に向けた計画を伝えるための「戦略的なツール」として活用しましょう。
2.「資金繰り」が鍵を握る理由
「うちはしっかり利益が出ているのに、なぜか銀行が融資してくれない…。」
そんな悩みを抱える経営者の方は少なくありません。決算書を見ると利益は黒字なのに、銀行の審査が通らない。その最大の原因は「資金繰り」にあります。利益は「儲け」を示す数字ですが、資金繰りは「手元にお金があるか」を示すものです。この両者は必ずしも一致しません。銀行員は利益だけでなくお金の流れ、つまりキャッシュが健全に回っているかを非常に重要視します。
(1)利益とキャッシュフローの決定的な違い
なぜ、利益が出ていても手元にお金がない状況が起こるのでしょうか。それは会計上の「利益」が、必ずしも現金収入を伴わないからです。例えば、1,000万円の商品を売ったとします。会計上は商品を引き渡した時点で「売上1,000万円」が計上され、利益が上がります。しかし顧客からの入金が3か月後だった場合、その3か月間は手元に1,000万円の現金はありません。この「売上計上から現金回収までのタイムラグ」や、在庫として仕入れた商品が売れずに現金化されない状況などが、黒字なのに資金繰りが悪化する「黒字倒産」の主な原因となります。銀行員は、このリスクがないかを決算書から徹底的に見抜こうとします。
(2)資金繰りの健全性を測る決算書のチェックポイント
では銀行員は、具体的に決算書のどの部分を見て資金繰りを評価しているのでしょうか。主に以下のポイントに注目します。
①キャッシュフロー計算書(C/F)
キャッシュフロー計算書は、会社の「お金の流れ」を記録したものです。この書類で最も重要なのが「営業活動によるキャッシュフロー」です。
【営業活動によるキャッシュフローがプラスか?】
これは、本業でどれだけのお金を稼いだかを示す数字です。これが継続的にプラスであれば、本業で安定して資金を生み出せている健全な状態と判断されます。逆に利益は出ているのに営業活動によるキャッシュフローがマイナスの場合、銀行は「この会社は利益を現金化できていない」と懸念し、融資に慎重になります。
②貸借対照表(B/S)
貸借対照表では会社の資産と負債の構成から、資金繰りの状況を読み解きます。
☆売掛金(売上債権)の増加
売掛金は、まだ入金されていない代金です。これが売上高の増加以上に増えている場合、代金回収が滞っていると見なされます。回収が
遅いと手元資金が減り、資金繰りが悪化します。
☆棚卸資産(在庫)の増加
商品や製品の在庫が増えすぎている場合、売れていない商品に資金が滞留していることになります。在庫は現金化されない限り、資金繰
りの足を引っ張る「不良資産」になりかねません。
☆買掛金(仕入債務)の状況
買掛金は、まだ支払っていない仕入代金です。これが売上や仕入に比べて急激に増えている場合、支払いを先延ばしにしていると見なさ
れ資金繰りに苦慮している兆候と捉えられることがあります。
(3)資金ショートのリスクをどう見極めているか
銀行員は、これらの数字の増減や比率を過去数年分にわたって比較・分析し、資金ショートのリスクを評価します。例えば「売上高は増加しているが、営業活動によるキャッシュフローがマイナス」かつ「売掛金と棚卸資産が大幅に増加している」という状況であれば、銀行は「将来的に資金ショートを起こす可能性がある」と判断し、融資を見送る可能性が高まります。融資を成功させるためには、利益を出すだけでなく健全なキャッシュの流れを築き、それを決算書から客観的に示せることが不可欠です。自分の会社の決算書が資金繰りの視点からどう見えるのかを事前にチェックし、万が一課題があれば、その改善策を銀行員に論理的に説明できるよう準備しておくことが、融資成功への確実な道となります。
3.事前準備で融資成功率を上げる方法
融資を申し込む際、決算書をただ銀行に提出するだけでは成功率はなかなか上がりません。決算書は、あなたの会社の過去の姿を語る「履歴書」のようなもの。その履歴書を単体で渡すのではなく「どのような思いで、どのような未来を描いているのか」をきちんと伝えることで、決算書を強力な「味方」に変えることができます。この記事では融資担当者に良い印象を与え、融資成功率を上げるための「決算書にプラスαで伝えるべき事前準備」について解説します。
(1)決算書の数字を「自分の言葉」で説明する
決算書の数字はただの記号ではありません。その一つひとつに、あなたの会社の歴史と努力が詰まっています。
①好調な数字は「なぜ伸びたのか」を語る
売上や利益が伸びている場合、その要因を具体的に説明しましょう。「新規顧客が増えた」「新商品のヒットで客単価が上がった」など具体的なエピソードを添えることで、数字の説得力が増します。
②不調な数字は「原因」と「改善策」を示す
もし赤字や資金繰りの悪化など良くない数字がある場合も、決して隠してはいけません。正直にその原因を認め「原材料の高騰が原因でした。今後は仕入先の見直しでコストを〇〇円削減します。」といったように、具体的な改善策を提示することが重要です。
銀行員は、数字の裏にあるあなたの経営者としての姿勢を見ています。数字に一喜一憂するだけでなく論理的に分析し、次へとつなげられる力があることをアピールしましょう。
(2)決算書の「未来」を語る事業計画書
決算書が過去の結果であるのに対し、事業計画書は未来への羅針盤です。決算書と事業計画書をセットで提出することで、あなたの会社が単なる「現状維持」の会社ではなく「成長」を目指している会社だと印象づけることができます。
①成長戦略を具体的に示す
「今後3年間で売上を2倍にします」という目標だけでなく「そのためにどうするのか」を具体的に示しましょう。「新商品を〇〇個開発し、新規顧客を〇〇人獲得する」といった具体的なアクションプランと、それに伴う売上やコストの予測を立てることが重要です。
②借入金の「使い道」を明確にする
融資を受ける目的を明確にしましょう。「新設備の導入費用として〇〇万円」「運転資金として〇〇万円」といったように、何にいくら使うのかを明確にすることで、銀行は融資の必要性を理解しやすくなります。
③返済計画を具体的に示す
「〇〇年〇〇月までに完済する」という目標に加え「新事業で得られる利益を返済に充てる」といったように、どうやって返済していくかを具体的に説明しましょう。これは銀行員にとって最大の関心事であり、信用を得る上で不可欠です。
(3)経営者自身の「熱意」と「誠実さ」を伝える
決算書や事業計画書は、あくまでツールです。最終的に銀行員が融資を判断するのは、経営者自身の「人柄」です。
①経営理念やビジョンを語る
「なぜこの事業をやっているのか」「社会にどう貢献したいのか」といった経営理念やビジョンを熱意を持って語りましょう。
②誠実な対応を心がける
銀行員からの質問には、たとえ耳の痛いことであっても誠実かつ正直に答えましょう。質問の意図を汲み取り論理的に説明する姿勢は、あなたの信頼性を高めます。
決算書を事前にしっかりと読み込み、会社の強みと弱みを深く理解する。そして数字の裏にあるストーリーや未来の計画を、自信を持って語る準備を整える。この事前準備こそが、融資成功への最も確実な一歩となります。決算書を単なる「提出書類」から、あなたの会社の「未来を語る最高のツール」へと変えていきましょう!
4.まとめ
「なぜ、あの会社は融資が通ったのに、うちの会社は駄目だったんだろう?」
この記事を読んで、そんな疑問が解消されたのではないでしょうか。融資の成功には、決算書の数字を正しく理解し、銀行員に会社の「健全性」と「将来性」を的確に伝えることが不可欠です。金融機関は、決算書の3つの書類(損益計算書、貸借対照表、キャッシュフロー計算書)から、会社の「収益性」「安全性」「資金繰り」を多角的に評価します。特に重要なのが、本業で安定してお金を生み出せているかを示す「資金繰り」です。利益が出ていても、手元に現金がなければ黒字倒産のリスクがあると判断されるため、キャッシュの流れを健全に保つことが非常に重要です。しかし、決算書はあくまで過去の姿を映し出す鏡に過ぎません。融資成功の鍵は、その鏡に映し出された現状を冷静に分析し「なぜそうなったのか」を自分の言葉で説明すること。そして「今後どう成長していくのか」を具体的な事業計画として提示することにあります。事前準備を徹底し、決算書の数字が持つ意味を深く理解する。そして、経営者自身の熱意と誠実さを伝える。これこそが決算書をただの書類から「会社の未来を語る最高のツール」へと変え、融資成功という未来を引き寄せる最も確実な方法です。