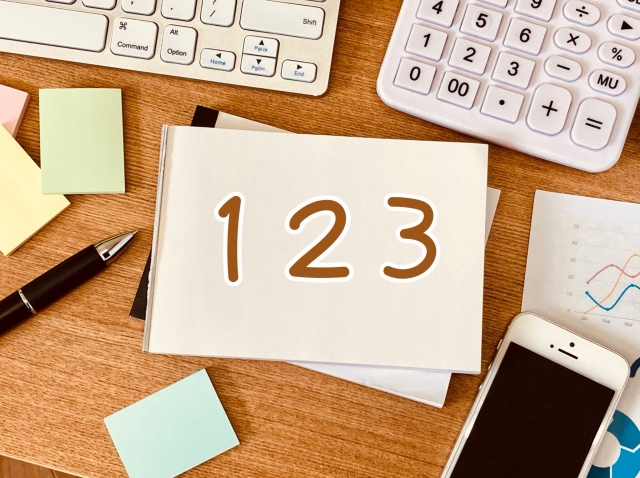会計・経理の基礎用語集~現場で使う言葉辞典~

目次
会計・経理の基礎用語集~現場で使う言葉辞典~
会計や経理の知識は、ビジネスを正しく理解するための基本です。
売上・利益・費用・税金など、数字の意味を正しく把握できれば、経営の判断もより正確になります。
この記事では、初心者にもわかりやすく「お金の流れ」「記帳と決算」「資金・税金・融資」の3つのテーマで、現場でよく使う会計・経理の用語を整理しました。
経営や独立を考える方、経理を基礎から学びたい方に役立つ内容です。
1. お金の流れが見える化する基本用語
ビジネスでは、「お金の流れ」を理解することが経営の第一歩です。
売上があっても利益がなければ事業は続きません。
ここでは「入ってくるお金」「出ていくお金」を見える化するための基本用語を整理します。
⑴売上・収益・利益
「売上」「収益」「利益」は混同されやすい用語です。
- 売上:商品やサービスの販売で得た金額。
- 収益:売上に利息収入なども含めた「会社が得たすべてのお金」。
- 利益:収益から費用を差し引いた残り。
利益には段階があります。主なものを理解しておきましょう。
⑵利益(・売上総利益・営業利益・経常利益・当期純利益)
- 売上総利益(粗利)
売上から仕入れ原価を引いた金額。 - 営業利益
本業による利益で、会社の実力を示します。 - 経常利益
営業利益に本業外の収支を加味した数値。 - 当期純利益
最終的に会社に残る利益。
どの利益を改善すべきかで経営判断が変わります。
⑶費用(変動費・固定費)
費用は、事業を行うために使ったお金です。
経費、仕入れ、人件費、家賃などが含まれます。
主な分類は以下のとおりです。
- 変動費:売上に応じて変動する費用(材料費・外注費など)
- 固定費:売上に関係なく発生する費用(家賃・人件費など)
費用を分けて管理することで、コスト構造が明確になります。
⑷原価と粗利
商品やサービスを作るために必要なお金を「原価」といいます。
原価には材料費や人件費などが含まれます。
例えば、原価500円の商品を1,000円で販売すれば、粗利は500円。
この粗利が高いほど利益を出しやすい構造といえます。
ただし固定費が高いと利益は圧迫されるため、バランスが重要です。
⑸損益分岐点
損益分岐点とは、売上と費用が同じになる点です。
このラインを超えて初めて利益が生まれます。
固定費100万円・変動費率50%の会社なら、
損益分岐点売上高は100万円 ÷(1−0.5)=200万円。
月商200万円を超えると黒字になります。
自社の損益分岐点を把握することは、経営安定の基礎です。
⑹在庫と在庫回転率
在庫は「まだ売れていない商品」であり、現金がモノの形で止まっている状態です。
在庫が多すぎると資金繰りを圧迫します。
効率を見る指標が「在庫回転率」です。
売上原価 ÷ 平均在庫高 で求められ、数値が高いほど在庫が早く回っています。
⑺キャッシュフロー
利益が出ていても、現金がなければ会社は続きません。
この現金の流れを「キャッシュフロー」といいます。
- 営業キャッシュフロー:本業での現金の増減
- 投資キャッシュフロー:設備投資など将来の支出
- 財務キャッシュフロー:借入や返済など資金調達
営業キャッシュフローがプラスであることが、健全な会社の目安です。
⑻売掛金・買掛金
売掛金は「商品を売って、まだ受け取っていないお金」。
買掛金は「仕入れて、まだ払っていないお金」。
信用取引の中核ですが、回収や支払いの時期がずれると資金繰りに影響します。
入出金のスケジュール管理が欠かせません。
⑴~⑻までがお金の流れを理解するための基本用語です。
経理初心者は、これらの言葉を経営の共通言語として少しずつ覚えていきましょう。
2. 記帳から決算まで
経理の仕事は、会社のお金の流れを正確に計上することから始まります。
日々の取引を整理し、定期的に集計することで、経営の状況が数字として見えるようになります。
ここでは、経理の現場でよく使われる基本用語を、初心者にもわかりやすく紹介します。
⑴記帳と仕訳について
「記帳」とは、お金の出入りを帳簿に記録することです。
その記録単位が「仕訳」です。
仕訳は、取引を左右2つに分けて記録します。
左を「借方(かりかた)」、右を「貸方(かしかた)」といいます。
例:備品を現金で1万円購入した場合
- 借方:備品 10,000円
- 貸方:現金 10,000円
このように「何に使ったお金か」と「どこから出たお金か」をセットで書くのが複式簿記です。
最初のうちは難しく感じますが、仕訳の型を覚えると帳簿付けが格段にスムーズになります。
⑵勘定科目について
仕訳をする際に使うのが「勘定科目」です。
勘定科目を正しく使うことで、数字の意味がはっきりします。
主な分類は次のとおりです。
- 資産:現金、預金、売掛金、備品
- 負債:買掛金、借入金、未払金
- 資本:資本金、利益剰余金
- 収益:売上高、受取利息
- 費用:仕入、給料、通信費、旅費交通費
事業内容によって使用する科目は異なります。
独自の勘定科目を追加しておくと、後の分析や税務処理がしやすくなります。
⑶帳簿と試算表
取引を日付順に記録したものが「仕訳帳」。
それを勘定科目ごとに集計したものが「総勘定元帳」です。
これらをまとめて作成するのが「試算表」です。
試算表を定期的に確認すると、
・収益と費用のバランス
・資産と負債の構成
・利益の増減の傾向
がひと目でわかります。
経営の現状をつかむ上で、試算表は非常に役立ちます。
定期的にチェックする習慣を持つことが、経理の精度を高める第一歩です。
⑷減価償却について
パソコンや車、機械など、長く使う設備は一度に全額を費用にできません。
使用年数に応じて少しずつ費用化する方法を「減価償却」といいます。
例:10万円のパソコンを5年間使う場合
→ 1年あたり2万円を費用として計上。
減価償却を正確に行うと、
- 利益計算が正確になる
- 節税効果が得られる
- 将来の資金計画が立てやすくなる
耐用年数や償却方法には法律上のルールがあるため、専門家に確認しておくと安心です。
⑸決算業務について
決算とは、1年間の取引をまとめて会社の経営状況を明らかにする作業です。
決算書は、いわば会社の成績表で、融資や補助金の審査などにも使われます。
主な決算書類は次の3つです。
- 損益計算書(PL):売上と費用を集計し、1年間の経営成績を示す。
- 貸借対照表(BS):資産・負債・純資産を一覧にし、財務の安定性を確認する。
- キャッシュフロー計算書(CF):利益と現金の動きのズレを把握する。
決算を通じて、事業の強みや課題が見えるようになります。
専門家の助言を受けながら進めると、数字の分析や改善策の発見につながります。
⑹青色申告とは
個人事業主やフリーランスは、正しい帳簿をつけることで「青色申告」ができます。
青色申告では、最大65万円の特別控除や、赤字の繰越控除などの特典を受けられます。
ただし、複式簿記での記帳が条件です。
最近はクラウド会計ソフトも普及していますが、仕訳や勘定科目の設定ミスには注意が必要です。
不安な場合は、会計の専門家に記帳方法を相談すると安心です。
日々の記帳を正しく行うことは、節税だけでなく事業の信頼にもつながります。
青色申告をきっかけに、自分の数字を理解し、経営をより安定させる意識を持ちましょう。
⑺記帳の目的
経理の目的は、税務署に報告するためだけではありません。
正確な帳簿は、取引先や銀行からの信頼を得るための土台になります。
また、数字を継続的に管理することで、経営の課題を早く発見できます。
記帳を負担の作業ではなく、経営の羅針盤として活用することが大切です。
数字を正しく扱うことが、結果的に事業の信頼と安定を生み出します。
3. 資金繰り・税金・融資の基本用語
経営において「お金を稼ぐこと」以上に重要なのが、お金を回す力=資金繰りです。
黒字でも現金が不足すれば、会社は動けません。
また、税金や融資の仕組みを正しく理解しておくことは、経営を安定させるための大切な土台です。
ここでは、日々の経営に直結する資金・税金・融資の基本用語を解説します。
⑴資金繰り
資金繰りとは、会社の手元資金を切らさないように管理することです。
「売上が上がっているのに現金が足りない」という状況は珍しくありません。
その原因の多くは、入金と支払いのタイミングのずれにあります。
よく使われる言葉を整理しておきましょう。
- 入金サイト:売上が入金されるまでの期間(例:請求書発行後30日など)
- 支払サイト:仕入れや経費の支払いまでの期間(例:翌月末払いなど)
- 運転資金:日常の経営活動に必要な資金。人件費、仕入れ、家賃などが含まれる。
入金サイトより支払サイトが短い場合、資金が一時的に不足することがあります。
そのため、現金残高を毎月管理する「資金繰り表」を作成しておくことが重要です。
資金繰りの基本は、
「売上を早く回収し、支払いを計画的に行う」
この一点に尽きます。
⑵税金の種類
事業を行う以上、避けて通れないのが税金です。
ここでは特に関係の深い3つの税金を押さえておきましょう。
・所得税(法人税)
事業の利益に対してかかる税金です。
個人事業主は「所得税」、法人は「法人税」となります。
経費を正しく計上することで、納税額を適正に抑えることができます。
・消費税
売上時に受け取った消費税を、仕入れなどで支払った消費税と差し引いて納税します。
「預かっているお金」であることを意識し、売上と同時に管理することが大切です。
消費税は納税時期の現金残高に影響するため、別口座で積み立てておく方法が有効です。
・源泉所得税
従業員の給与や外注費を支払う際に、支払側があらかじめ税金を差し引いて納める制度です。
支払時点で源泉徴収を行い、翌月10日までに納付します。
これらの税金を理解しておくことで、納税の見通しを立てやすくなります。
税金は「あとから払うもの」ではなく、「毎月準備しておくもの」と考えるのが安全です。
⑶節税とは
節税とは、法律の範囲内で納税額を抑える工夫のことです。
ただし、「支出を増やして節税する」だけでは現金が減るため、バランスが重要です。
代表的な方法をいくつか紹介します。
- 減価償却の活用:資産を分割して費用化し、利益を平準化する。
- 小規模企業共済への加入:将来の退職金準備をしながら所得控除を受けられる。
- 倒産防止共済の利用:もしもの時の備えと節税を兼ねられる制度。
節税は「目先の利益を減らすこと」ではなく、
将来に向けた資金のコントロールと考えると、判断を誤りません。
⑷融資について
会社の資金を補う手段の一つが「融資」です。
融資を受ける目的は、赤字補填ではなく、成長への投資であることを意識しましょう。
融資の基本用語を理解しておくと、金融機関とのやり取りがスムーズになります。
- 自己資本比率:会社の安定性を示す指標。高いほど評価されやすいです。
- 返済能力:本業の利益で返済できるかを判断するための基準です。
- 担保・保証人:融資を受ける際に求められることがあります。
- 信用情報:過去の取引や返済状況の記録。信頼の基盤となります。
融資を受ける際は、決算書類や経営資料の整備が欠かせません。
数字の根拠を明確にし、返済計画を具体的に示すことで、金融機関からの信頼を得られます。
⑸補助金・助成金
近年は、国や自治体が中小企業・個人事業主向けに多くの支援制度を設けています。
代表的なものは、
- 事業再構築補助金
- 小規模事業者持続化補助金
- 雇用関係助成金
これらは返済不要の資金であり、うまく活用すれば資金繰りの負担を軽くできます。
ただし、申請には書類作成や実績報告が必要なため、早めの情報収集と準備が大切です。
⑹資金管理の基本は「見通し」と「信頼」
資金繰り、税金、融資のどれも、単独で成り立つものではありません。
お金の流れを見通し、信頼される記録を積み重ねていくことが経営の安定につながります。
数字をただ記録するだけでなく、経営の舵を取るための情報として活かす意識を持ちましょう。
それが、経理の本当の力を引き出す第一歩です。
まとめ
会計や経理の知識は、どんな業種にも共通して役立ちます。
「売上」「費用」「利益」といった基本用語から、「仕訳」「決算」「資金繰り」まで、すべては会社のお金を見える化するための道具です。
これらの言葉を理解し、正しく使えるようになると、経営状況の変化にすぐ気づけるようになります。
また、数字をもとにした判断ができるようになり、無駄な支出を減らし、投資や融資のタイミングも的確に見極められます。
経理は「過去を記録する仕事」ではなく、「未来をつくる仕事」です。
日々の数字をただ処理するのではなく、そこから経営の方向性を読み取る力を身につけていきましょう。
その積み重ねが、事業の信頼と成長を支える大きな力になります。