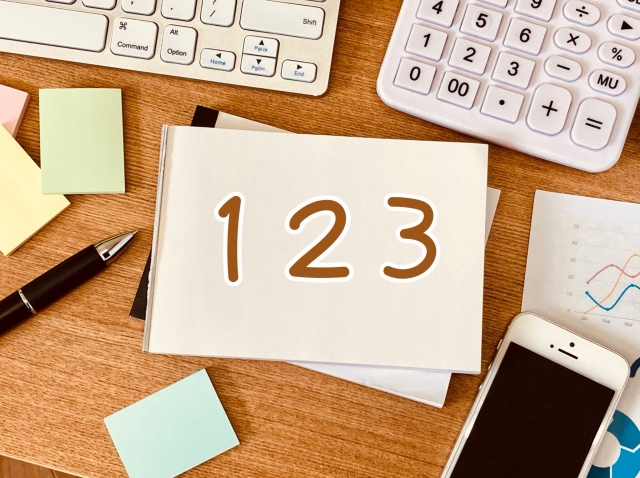会社のお金の流れをつかむ!~キャッシュフローの超入門~

目次
会社のお金の流れをつかむ!~キャッシュフローの超入門~
家計と会社の最も大きな違いの一つは、会社には「お金の流れ」を把握するための専門的な指標があることです。個人の家計簿にあたる「会社の成績表」には、損益計算書(P/L)、貸借対照表(B/S)、そして今回のテーマであるキャッシュフロー計算書(C/F)の3種類があります。「なんだか難しそう…。」と感じる方もいるかもしれませんが、安心してください。この記事ではキャッシュフローについて、基本的なことから丁寧に解説していきます。経営者や起業家はもちろん、会社の財務状況に関心があるすべての人にとって、キャッシュフローを理解することは、成長を加速させ予期せぬ危機を乗り越える力をつけることにつながります。ぜひ、最後までお読みください!
1.キャッシュフローとは?
会社の健康状態って、どうやって判断すると思いますか? 多くの人が「利益が出ているかどうか」を思い浮かべるかもしれませんね。たしかに利益は大切です。でも、実は利益だけでは会社の本当の姿は見えてこないんです。そこで登場するのが、会社の血液ともいえる「お金の流れ」つまりキャッシュフローです。キャッシュフローを把握することは、会社の健康状態を把握することと同じです。まるで『健康診断の成績表』のようなもの。利益だけを見て「健康だ!」と判断するのではなく、実際に血液(お金)がスムーズに流れているかを確認することが、会社の持続的な成長には不可欠なんです。キャッシュフローを具体的に把握するために使われるのが「キャッシュフロー計算書」です。これは、会社のお金の出入りを以下の3つの活動に分けて示しています。この3つの視点で見ると、会社がどのようにしてお金を生み出し使っているのかが一目で分かります。
(1)営業活動によるキャッシュフロー → 本業で稼いだお金の流れ
これは会社の本業である商品やサービスの販売、仕入れといった通常の営業活動から生じるお金の流れを示します。
【プラスの場合】
本業が順調でしっかりとお金を稼げている証拠です。これがプラスであることは、会社の安定性を測る上で最も重要な指標の一つと言えます。
【マイナスの場合】
本業が苦戦している、または売上はあっても回収が遅れている可能性があります。もし継続的にマイナスが続くようであれば、早急な対策が必要です。
イメージは、お店のレジです。お客様がお金を払ってくれて、レジにお金が入ってくる。そして仕入れのお金を払ったり、電気代を払ったり、お給料を払ったりして、レジからお金が出ていく。その最終的にレジに残ったお金が、この「営業活動によるキャシュフロー」に入っていると考えれば分かりやすいでしょう。つまり「営業キャッシュフローが安定してプラスであること」は会社の健全な経営の基本中の基本なんです。
(2)投資活動によるキャッシュフロー → 将来のために使ったお金の流れ
これは、会社が将来の成長のために行った投資に関するお金の流れを示します。具体的には工場や機械の購入、他社の買収、有価証券の購入などがこれにあたります。
【プラスの場合】
固定資産の売却や有価証券の売却などで、現金を得ていることを示します。事業の縮小や、資金繰りのために資産を売却している可能性もあります。
【マイナスの場合】
設備投資やM&Aなど、積極的に将来への投資を行っていることを示します。これは、将来の成長を見据えた前向きな活動と捉えられます。ただし、投資内容が適切であるかは見極めが必要です。
イメージは、自己投資です。あなたがスキルアップのために本を買ったり、セミナーに参加したりするようなものです。今すぐ収入が増えるわけではないけれど、将来のためにお金を使っていますよね。あるいは、使わなくなったブランド品を売ってお金に変えるようなことも対象となると考えられます。投資キャッシュフローは、マイナスであることが必ずしも悪いわけではありません。むしろ成長企業であれば積極的に投資を行うため、マイナスになる傾向があります。
(3)財務活動によるキャッシュフロー → 資金の調達と返済のお金の流れ
これは銀行からの借入や社債の発行などによる資金調達、あるいは借入金の返済や配当金の支払いなど、資金の調達と返済に関するお金の流れを示します。
【プラスの場合】
新たな借入や増資などで資金を調達していることを示します。事業拡大のための資金調達や、一時的な資金不足を補っている可能性があります。
【マイナスの場合】
借入金の返済や配当金の支払いなどを行っていることを示します。これは、自己資金で事業を回せている健全な状態とも言えますが、逆に返済負担が大きい場合もあります。
イメージは、あなたのお財布と銀行のやり取りです。急な出費でお金が足りなくなった時、親や銀行からお金を借りてお財布に入れるのがプラスの動き。お給料が入って、借りたお金を返済したり貯金したりするのがマイナスの動き、といった具合です。財務キャッシュフローもプラスだから良い、マイナスだから悪いと単純には言えません。例えば、健全な企業が借入金を計画的に返済している場合はマイナスになりますし、一方で資金繰りに困って借入を増やせばプラスになるからです。
(4)利益とキャッシュフロー → 会社の健全性を測る二つの視点
利益は「儲かっているか」を示しますが、キャッシュフローは「潰れないか」を示します。会社の「健康状態」を本当に把握するためには、この両方をバランス良く見ていく必要があるのです。キャッシュフローを理解する第一歩は、まず自社のキャッシュフロー計算書を見てみることです。もし会計士や税理士にお願いしているのであれば、一度説明を求めてみましょう。難しく感じるかもしれませんが、3つの活動に分けて見れば意外とシンプルなことがわかるはずです。そして日々の資金繰りを意識し、お金がいつ入ってきて、いつ出ていくのかを予測する習慣をつけましょう。会社の「お金の成績表」であるキャッシュフローを読み解く力は、経営者にとって必須のスキルです。今日からぜひ、自社のキャッシュフローに目を向けてみてください。きっと、会社の未来をより確かなものにするヒントが見つかるはずです。
2.キャッシュフローが会社の倒産を防ぐ理由
「うちは利益が出ているから大丈夫!」多くの経営者の方がそう考えているかもしれません。実際、売上が伸びて利益も順調に積み上がっている会社を見ると「この会社は安泰だ。」と思いがちですよね。でも実はその「利益」だけを見て安心していると、思わぬ落とし穴にはまることがあります。それが「黒字倒産」という恐ろしい事態です。
(1)利益があっても倒産する「黒字倒産」の恐怖
黒字倒産とは文字通り会計上の利益は出ているのに、手元に現金がないために支払いができなくなり倒産してしまうことを指します。「そんなバカな話があるのか?」と思うかもしれませんが、これは決して珍しいことではありません。身近な例で考えてみましょう。例えば、あなたが小さな洋服店を経営しているとします。
①1月
冬物セールの大ヒットで、100万円分の洋服を売り上げました。でもお客様のほとんどがツケ払い(クレジットカードや後払い)で、入金は翌月末です。
②2月上旬
従業員の給料、家賃、電気代、そして次の春物の仕入れ代金など、合計80万円の支払い期限が迫っています。
③2月下旬
1月に売り上げた100万円がようやく入金されました。
このケースだと、1月の売上は100万円で仕入れや経費を差し引いても利益は出ているはずです。しかし2月上旬の支払いの段階では、まだ1月分の売上が手元にありません。もし銀行に預金がなかったり他の入金が間に合わなかったりすると、80万円の支払いができませんよね? これがまさに、黒字倒産の典型的な例です。利益は出ていても、手元に現金がなければ会社は回りません。
(2)黒字倒産が起こる主な原因
なぜ黒字倒産が起きてしまうのでしょうか? 主な原因はいくつかあります。
①売掛金の回収サイトが長い(入金が遅い)
商品を販売しても、すぐにお金が入ってこないケースです。BtoB(企業間取引)では特に多く月末締め翌月末払い、あるいは翌々月末払いといった条件は一般的です。
②棚卸資産(在庫)が過剰
売れ残りの商品がたくさんあると、それを作るためのお金はすでに支払っていますが、現金化できません。在庫が多すぎるとお金が滞留してしまいます。
③設備投資や先行投資の多用
新しい機械の導入や大規模なプロモーションなど将来の成長のための投資は必要ですが、その支出が会社の現金を大きく圧迫することがあります。投資に見合うだけの売上や入金がすぐに発生しない場合、資金繰りが苦しくなります。
④突発的な大きな支払い
予期せぬトラブルによる修理費用や税金の支払いなど、突然の大きな出費が資金繰りを悪化させることもあります。
⑤利益と現金のズレの認識不足
これが最も根本的な原因かもしれません。多くの経営者が損益計算書(利益が出ているかを見る表)はしっかり見ていても、キャッシュフロー計算書(現金の流れを見る表)の重要性を認識していないために、気づかないうちに資金がショートしてしまうのです。
(3)「お金の流れ」が見えれば会社は強くなる!
多くの経営者は、会社の成績を利益で判断しがちです。しかしやはり、忘れてはならないのは「お金の流れ」つまりキャッシュフローです。この流れをしっかり把握することで会社は倒産のリスクを避け、より強く成長できます。その具体的な利点を以下に4つご紹介します。
①資金ショートの予知と対策
キャッシュフローを定期的に把握することで、「〇月にはこれだけの支払いがあるのに、入金がこれだけしかないから、△△円足りなくなるな。」というように将来の資金不足を事前に予測できます。 予測ができれば、例えば銀行に融資の相談をしたり、売掛金の早期回収を交渉したり、経費の支払いを一時的に延期してもらったりと、手を打つ時間的猶予が生まれます。これができずに直前になって「お金がない!」となると、もう手遅れになることが多いのです。
②経営判断の質向上
新しい事業への投資、設備の購入、人材の増強など、経営には常に意思決定が伴います。その際、利益が出るかどうかだけでなく「その投資によっていつ、どれくらい現金が出ていくのか?」「その支出を賄うだけの現金が手元にあるか?」という視点を持つことが重要です。 例えば「この機械を買えば、将来的に大きな利益を生むだろう。」と思っても、購入時に多額の現金が流出しその後の資金繰りが立ち行かなくなるようでは本末転倒です。キャッシュフローを考慮に入れることで、より現実的で安全な経営判断ができるようになります。
③銀行・取引先との信頼関係構築
キャッシュフローをきちんと把握しそれを説明できることは、銀行からの信頼を得る上で非常に有利です。銀行は会社が「利益が出ているか」だけでなく、「ちゃんと借入を返済できるだけの現金があるか」を重視します。「資金繰り表」などでキャッシュフローを提示できれば、銀行も安心して融資に応じやすくなります。また取引先との支払い条件交渉などでも自社の資金状況を正確に伝えることができ、より円滑な関係を築けます。
④事業の継続性と成長性の確保
結局のところ会社が存続し成長していくためには、常に「血液」である現金がスムーズに循環していることが不可欠です。利益が出ていても現金がなければ、給料も払えず仕入れもできず事業はストップしてしまいます。 キャッシュフローを健全に保つことで不測の事態にも対応でき、新たなビジネスチャンスにも迅速に投資できる「足腰の強い会社」を作り上げることができるのです。
3.まとめ
すでにお伝えしたように会社経営では利益が「儲かっているか」を示す一方で、キャッシュフローは「潰れないか」という会社の生命線を握っています。会計上の利益が出ていても、手元に現金がなければ支払いが滞り「黒字倒産」の危機に直面する可能性があるため、この二つの視点をバランス良く持つことが不可欠です。
キャッシュフロー計算書は、会社の「お金の成績表」であり、「営業活動」「投資活動」「財務活動」という3つの視点からお金の出入りを明らかにします。C/Fを理解し活用することで将来の資金不足を事前に予測し、適切な対策を講じることが可能になります。これにより資金ショートを防ぎ、より現実的で安全な経営判断を下せるようになります。
またキャッシュフローを適切に管理し説明できることは、銀行や取引先との信頼関係構築にもつながり、事業の継続性と成長性を確かなものにします。利益が会社の「顔」であるならば、キャッシュフローは会社の「心臓」です。心臓が止まれば会社は存続できません。今日から自社のキャッシュフローに目を向けその動きを読み解く力を養うことが、会社の未来を築くための最も確実な一歩となるでしょう。