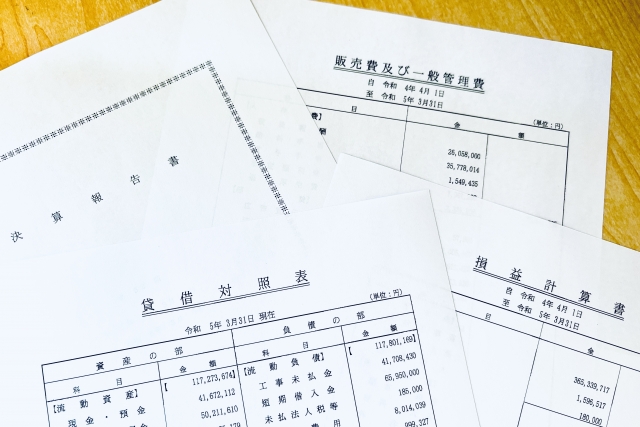インボイス制度の少額特例とは?いつまで使えるか
目次
そもそもインボイス制度とは
仕入税額控除
消費税は消費者が負担しますが、納税は課税事業者が行います。課税事業者は、売上げに係る消費税額から、仕入れに係る消費税額を差し引いて計算した額を納税します。
売上で受け取った消費税額から、仕入れで支払った消費税額を差し引くことを「仕入税額控除」と言います。
具体的には、消費税として税務署に納める金額は、次の計算方法で計算します(原則課税)。
インボイス制度の概略
インボイスの保存が必須
2023年10月にインボイス制度がはじまると、この仕入税額控除をするためには、原則として、仕入先からインボイス(適格請求書)を発行してもらい、保存しておく必要があります。
インボイス発行できるのは登録事業者のみ
このインボイスは、税務署長の登録を受けたインボイス発行事業者(登録事業者)のみが発行できます。つまり、仕入先にインボイスを発行してもらうには、仕入先が税務署にインボイス事業者として登録する必要があります。つまり、仕入先がインボイス発行事業者であるか確認する作業が必要となってきます。
仕入先がインボイスを発行してくれないと納税額が増える
仮に、仕入先がインボイス発行事業者ではなかった場合、そこから仕入れた取引は、仕入税額控除ができず納税する消費税の額が増えてしまいます。
売り手と買い手の義務
<売手側>
売手である登録事業者は、買手である取引相手(課税事業者)から求められたときは、インボイスを交付しなければなりません(また、自らが交付したインボイスの写しを保存しておく必要があります)。
<買手側>
買手は仕入税額控除の適用を受けるために、原則として、取引相手(売手)である登録事業者から交付を受けたインボイスの保存等が必要となります。
ただし例外として、買手はインボイスの保存に代えて、買手が自ら作成した仕入明細書等のうち「一定の事項(インボイスに記載が必要な事項)が記載され取引相手の確認を受けたもの」を保存することで、仕入税額控除の適用を受けることもできます。
インボイス制度の少額特例とは
少額(税込1万円未満)の課税仕入れについて、インボイスの保存がなくとも一定の事項を記載した帳簿の保存のみで仕入税額控除ができるという制度です。
インボイス制度においては、原則的にインボイスを保存しなければ仕入税額控除ができません。しかし、この少額特例が適用されるケースでは、税込1万円未満の商品などを購入した際に、要件を満たしている事業者であれば、インボイスの保存がなくても一定の事項を記載した帳簿の保存のみで仕入税額控除ができます。
少額特例の注意点
免税事業者から仕入れる場合
少額特例においては、仕入先が課税事業であるか適格請求書発行事業者であるかは関係ありません。あくまでも、税込1万円未満の課税仕入れであれば、免税事業者から仕入れた場合でも少額特例の対象となります。
税込1万円未満の判定単位
少額特例は、一取引当たり税込1万円未満の課税仕入れが対象となります。この判定基準は、一取引ごとに毎回適用されます。商品ごとの金額ではなく、一取引ごとの金額である点に注意が必要です。
「税込1万円未満の課税仕入れ」に該当するか否かについては、一回の取引の課税仕入れに係る金額(税込み)が1万円未満かどうかで判定するため、課税仕入れに係る一商品ごとの金額により判定するものではありません。
したがって、3,000円の商品と8,000円の商品を同時に購入した場合は合計11,000円ですので、少額特例の対象とはなりません。
インボイスの発行義務は免除されない
少額特例は、少額の課税仕入れについて、インボイスの保存を不要とするものであり、インボイス発行事業者の交付義務が免除されているわけではありません。そんため、インボイス発行事業者は課税事業者からインボイスを求められた場合には交付する義務があります。
少額特例の帳簿記載要件
前述のとおり、少額特例を適用する場合はインボイスの保存は不要ですが、「一定の事項」を記載した帳簿を保存することが必要です。この一定の事項とは、次のものをいいます。
1,課税仕入れの相手方の氏名又は名称
2,取引年月日
3,取引内容(軽減税率対象の場合、その旨)
4,課税仕入れに係る支払対価の額
少額特例の適用対象者
少額特例の適用対象者は、基準期間における課税売上高が1億円以下、または特定期間における課税売上高が5千万円以下の事業者です。
ただし、特定期間における課税売上高については、納税義務の判定における場合と異なり、課税売上高に代えて給与支払額の合計額による判定はできません。
「基準期間」とは、個人事業者の場合はその年の前々年、事業年度が1年である法人の場合はその事業年度の前々事業年度のことをいいます。
「特定期間」とは、個人事業者については前年1月から6月までの期間をいい、法人については前事業年度の開始の日以後6月の期間をいいます。
少額特例はいつまで使えるか
少額特例は、令和5年10月1日から令和11年9月30日までの期間が適用対象期間となります。
なお、令和5年10月1日から令和11年9月30日までの間に行う課税仕入れが適用対象となりますので、たとえ課税期間の途中であっても令和11年10月1日以後に行う課税仕入れについては、少額特例の対象とはなりません。
令和11年10月1日以後に行う課税仕入れについては、仕入税額控除を受けるためには、原則として、インボイスと一定の事項を記載した帳簿の保存が必要となりますので注意しましょう。
免税事業者から仕入れた場合も少額特例の対象になる
少額特例においては、仕入れ先が課税業者、免税業者のいずれでも対象になります。たとえ免税事業者から仕入れた場合でも、取引金額が税込1万円未満であれば対象となります。少額特例は、仕入れ先が課税業者か免税業者かで扱いが変わることはありません。
国税庁参考サイト
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/shohi/kaisei/202304/02.htm
執筆者:税理士 渕上 肇