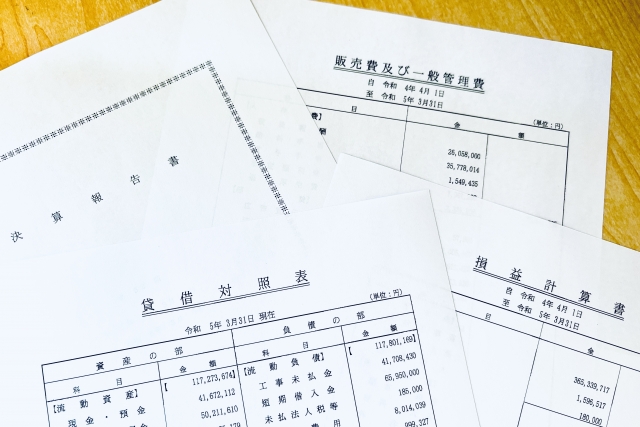はじめての会計入門!数字が苦手でもわかる“お金の流れ”の基本

はじめての会計入門!数字が苦手でもわかる“お金の流れ”の基本
数字が苦手でも、会計は少しずつ理解できます。
大切なのは、完璧に覚えることより「慣れること」。
この記事では、会計を身近に感じるための3つのステップを紹介します。
⒈会計の基本を理解しよう
(1)会計とは何か
「会計」という言葉は、むずかしく聞こえますが、やっていることはシンプルです。
会社の中で動く「お金の流れ」を整理して、わかるようにする仕組みです。
たとえば、お客様からの入金や、仕入れにかかった支出。
給与の支払い、家賃、光熱費など、会社では毎日たくさんのお金が動きます。
それらを放っておくと、「今いくら残っているのか」「どれだけもうかっているのか」がわからなくなります。
そこで必要になるのが会計です。
お金の動きをきちんと記録し、整理して、会社の状況を数字で確認できるようにします。
つまり、会計は経営の全体を見える化するための道具なのです。
(2)会計が果たす役割
会計には、主に次のような役割があります。
- 経営の状態を把握すること
今の会社が黒字なのか赤字なのかを知るために必要です。
売上や経費を整理することで、「利益が出ているか」を確認できます。 - 将来の判断に使うこと
数字をもとに、来月の支出を抑えたり、新しい設備投資を考えたりできます。
感覚ではなく、数字で考えることが経営の安定につながります。 - 関係者に正確な情報を伝えること
銀行、税務署、取引先などに信頼してもらうために、正しい会計が欠かせません。
会計の数字は、いわば会社の「共通の言葉」です。
(3)会計と経理の関係:毎日の記録から全体の判断へ
会計と経理は、似ているようで役割が少し違います。
- 経理は、毎日の取引をひとつずつ「記録する」仕事です。
売上や仕入れ、経費の支払いなどを正確に書きとめ、数字の材料を集めます。 - 会計は、その記録をまとめて「全体を整理し、判断する」仕事です。
集められた数字を見て、会社の状態を読み取り、次の行動を考えます。
経理がなければ、会計のもとになる数字がありません。
会計がなければ、記録を活かして経営判断をすることができません。
つまり、この二つは「毎日の積み重ね」と「全体の把握」という関係にあります。
(4)会計は会社のお金の通り道を整える仕組み
会計のイメージを、もう少し具体的にしてみましょう。
会計は、会社の中を流れるお金の通り道を整える仕組みです。
お金が入るところ(売上)、出ていくところ(仕入れや経費)、
残るところ(利益)をきちんと整理して、全体の流れを見えるようにします。
この仕組みがあることで、どこでお金が増え、どこで減っているかがわかります。
結果として、経営者は数字を見て「改善すべき点」や「投資すべき分野」を判断できます。
(5)会計の基本は「正確に記録し、整理する」こと
どんなに規模の大きい会社でも、会計の基本は同じです。
日々の取引を正確に記録し、それを整理すること。
これが、すべての会計の出発点です。
数字を正しく残すことで、将来の経営判断に役立つデータが蓄積されます。
逆に、記録があいまいだと、正しい判断ができません。
会計とは、「お金の動きを正確に残し、経営を整えるための基礎作業」。
難しい計算や専門用語よりも、まずはこの考え方をしっかり理解することが大切です。
⒉売上・経費・利益のつながりを見える化する
(1)「お金の流れ」は3つの要素でできている
会社のお金の動きは、基本的に次の3つで成り立っています。
- 売上(入ってくるお金)
- 経費(出ていくお金)
- 利益(残るお金)
この3つがどのようにつながっているかを理解すると、経営の状態を数字でつかめるようになります。
それぞれの意味を順番に見ていきましょう。
(2)売上とは「活動の成果」
売上は、会社の活動によって得られたお金です。
商品を売ったり、サービスを提供したりして得た収入がこれにあたります。
たとえば、1杯500円のコーヒーを100杯売れば、売上は5万円です。
売上が大きいほど、会社の活動が活発に行われているということになります。
ただし、売上が多いからといって、すぐにもうかっているとは限りません。
なぜなら、そこには「経費」という出ていくお金があるからです。
(3)経費とは「活動に必要な支出」
経費は、売上を得るために使ったお金のことです。
材料費、人件費、家賃、光熱費、広告費などが代表的です。
会社を動かすには、必ず経費がかかります。
経費が多すぎると、売上があっても利益が残りません。
反対に、必要な経費を削りすぎると、サービスの質が下がることもあります。
つまり、経費は「減らせば良い」というものではなく、
売上とのバランスを取ることが大切です。
(4)利益とは「会社に残る成果」
売上から経費を引いた残りが「利益」です。
利益 = 売上 − 経費
利益が出ていれば、会社は健全にお金を生み出していることになります。
利益が出ない状態が続くと、どんなに売上があっても経営は苦しくなります。
利益は、会社の将来を支える原資でもあります。
たとえば、設備を新しくしたり、社員に還元したりするのも利益があるからこそ可能です。
(5)売上・経費・利益の関係をイメージする
3つの関係を、頭の中で流れとしてイメージしてみましょう。
- 商品やサービスを販売して「売上」が入る
- 材料費や人件費などで「経費」が出ていく
- その差額として「利益」が残る
この流れを「入る → 出る → 残る」と覚えると、
お金の動きがシンプルに理解できます。
(6)利益が出ているのにお金が足りないのはなぜ?
会社の会計では、「利益」と「現金」は必ずしも同じではありません。
利益が出ているのにお金が足りないことがあります。
たとえば、次のようなケースです。
- 売上は計上されているが、まだ入金されていない(売掛金)
- 設備投資や借入金の返済で現金が減っている
- 仕入れの支払いタイミングが重なった
このように、「利益」は数字上の結果であり、実際の手元資金とはズレることがあります。
このズレを管理するのが「資金繰り」や「キャッシュフロー」です。
(7)数字を「つながり」で見ることが大切
会計の数字を正しく読むためには、それぞれを単体で見るのではなく、「つながり」で考えることが重要です。
- 売上が増えた → 経費も増えていないか?
- 利益が減った → 原価や固定費が上がっていないか?
- お金が足りない → 入金のタイミングが遅れていないか?
このように、数字を「点」ではなく「線」で見ると、経営の状態がはっきりと見えてきます。
(8)お金の動きを見える化する習慣をつけよう
お金の流れは、頭の中で考えているだけではすぐにあいまいになります。
だからこそ、数字で「見える化」することが大切です。
たとえば、
- 月ごとの売上と経費をノートに書き出す
- どの費用が増えているかを毎月チェックする
- 利益が減ったときは原因を一つずつ確認する
こうした習慣をつけるだけで、経営の見通しがずっと良くなります。
数字に苦手意識がある人も、まずは「売上」「経費」「利益」の関係を
毎月一度だけでも確認してみましょう。
お金の流れを意識することが、会計を理解する第一歩になります。
⒊数字が苦手でも大丈夫!会計を理解する3つのステップ
(1)ステップ1:数字を「意味」で覚える
会計の数字が苦手な人の多くは、「数字だけを暗記しよう」としてつまずいています。
大切なのは、数字を意味で覚えることです。
たとえば、売上が「会社の活動の結果」、
経費が「活動にかかったコスト」、
利益が「成果の残り」と理解できれば、
数字の並びが自然と頭に入ってきます。
数字を「難しいもの」ではなく、「仕事の結果を表す言葉」として見るようにしましょう。
- 売上が増えた=お客様が増えたサイン
- 経費が増えた=必要な投資か、無駄な支出かを確認する合図
- 利益が減った=改善のチャンスがある状態
このように、数字を単なる計算ではなく、「会社のストーリーを映すもの」として捉えると理解が深まります。
(2)ステップ2:日常生活の中で会計を意識する
会計を理解する近道は、身近なお金の動きに目を向けることです。
たとえば次のように考えてみましょう。
- コンビニで買い物をした → 「経費」が発生した
- お給料が入った → 「売上」が発生した
- 月末に貯金が残った → 「利益」が出た
このように、自分の生活を「小さな会社」に置き換えて考えると、会計の感覚が自然と身につきます。
また、家計簿やスマホの支出アプリも良い練習になります。
毎日の記録をつけることで、数字の変化を実感できます。
「なぜ今月はお金が残らなかったのか?」と考える習慣が、会計的な視点を育てる第一歩です。
(3)ステップ3:ツールを使って“見える化”する
最近では、会計ソフトやクラウドツールが充実しています。
難しい計算をしなくても、入力するだけで自動的に整理してくれます。
代表的なものとして、
- freee
- マネーフォワードクラウド
- 弥生会計オンライン
などがあります。
こうしたツールを使うと、
グラフや表でお金の流れが「見える化」されます。
数字を眺めるよりも、色や動きで理解できるため、苦手意識を減らすことができます。
また、クラウド会計なら銀行口座やクレジットカードと連携でき、自動で取引を記録してくれるため、作業の負担も軽くなります。
まずは「数字を入力する」「グラフを見てみる」など、できるところから始めてみましょう。
(4)会計を理解するための3つのコツ
会計を学ぶうえで意識しておきたい基本のコツがあります。
- 「完璧に理解しよう」としないこと
最初から全部覚えようとすると、かえって混乱します。
まずは「なんとなくわかる」で十分です。 - わからない言葉は調べながら進めること
難しい用語に出会ったら、辞書やネットで軽く意味を確認します。
その都度理解することで、少しずつ知識が積み重なります。 - 実際の数字を見て慣れること
本や講義だけでなく、自分の売上や支出などの“生きた数字”を見ると、
理解のスピードが格段に上がります。
会計は、理屈よりも「慣れ」で理解が進む分野です。
数字を見る時間を少しずつ増やすことで、自然と“会計の目”が育っていきます。
(5)会計を知ると見えてくる3つの変化
数字に慣れてくると、仕事の見方が変わります。
- 無駄な支出に気づける
数字を見ることで、「この経費は必要か?」と考えられるようになります。 - 会社のお金の使い方に興味が出る
「どうすれば利益を増やせるか」を自然に考えるようになります。 - 数字に対する自信がつく
苦手だと思っていた会計が、意外とシンプルに感じられるようになります。
このように、会計を理解することは、単に数字を扱うスキルではなく、
仕事全体を整理して考える思考のトレーニングでもあります。
(6)少しずつ慣れていくことが一番の近道
会計は、一度にすべてを理解する必要はありません。
最初は「数字を見慣れる」「意味を知る」だけで十分です。
少しずつでも続けていけば、いつの間にか数字を見ることに抵抗がなくなります。
焦らず、毎日少しずつ慣れていくこと。
それが、数字が苦手な人にとって一番の学び方です。
まとめ
会計を理解することは、数字を読み取るだけでなく、
仕事やお金の流れを客観的に見る力を身につけることでもあります。
最初は「数字を見るのが苦手」と思っていても大丈夫です。
数字を意味として捉え、日常の中でお金の動きを意識し、 ツールを使って見える化する。
この3つを続けることで、会計は少しずつ自分の中に定着していきます。
焦らず、できることから始めることが何より大切です。
数字が読めるようになると、仕事の判断が明確になり、お金との付き合い方も変わっていきます。
小さな一歩が、確かな経営力への第一歩になります。